ISSF公式からの中継動画やツイートなどで既に把握されてる方もいらっしゃるかもしれませんが、ドイツのズールで開催されているISSFジュニアワールドカップでは、ファイナルに限って選手の銃にSCATTを取り付け、そこから得られる軌跡データを中継動画に差し込むという演出が行われています。
Electric energy, focused minds, and roaring support! 🔊✨
The 10m Air Pistol Mixed Team Junior final in Suhl had it all!#ISSF #ISSFJuniorWorldCup #ShootingSports pic.twitter.com/08ndB4aXGV
— ISSF (@issf_official) May 22, 2025
見た目の動きがほとんどないライフル射撃というスポーツですが、実際にやってる側からすると「とんでもなく大きな動き」があり、時には緊張で時には疲労で一気に暴れだしそうになるその動きを必死になって制御し続けようとする、そういうスポーツだったりします。
しかし、画面では銃口の動きなんてほとんど分かりません。構えてから狙って実際に撃つまでの、そりゃもうドラマチックなんてもんじゃない「あれこれ」は視聴者には全く伝わらず、撃った結果として表示される着弾位置しか視聴者には伝わらないわけです。
例えば陸上競技でいうなら、スタートしてからゴールするまではトンネルの中をずっと走ってて、視聴者は全くその様子が見えないようなもんです。視聴者が見ることができるのはゴールしたタイム、その数字だけ――そんなん見てて面白いわけないですよね。
その「伝わりづらい、途中経過のドラマチックなところ」をなんとかして視聴者に伝えるためには何をすればいいのか、ということで以前から言われていたのが「選手の銃にSCATTを取り付けて、軌跡が観客に見えるようにしたら盛り上がるんじゃね?」ってやつです。うまい具合に構えることができて「これもういつ撃っても10点間違いない」なホールドができてたりしたら観客は「今だーっ、撃てーっ撃てーっ」って気持ちになりますし(実際にそれを声にだしたりしたらダメだと思いますが)、その後にホールドが崩れて大きく軌跡が散らばりだしたら「ああーっだめだめだめーっ撃つなーっ」って気持ちになると思います。想像するだけでこっちの心臓がどうにかなりそうなくらいのエキサイティングな中継になりそうです。
それを実際にやってみたのが、今回のISSFジュニアワールドカップということらしいです。
早速、海外の射撃競技専門BBSであるTargetTalkでも話題になっていましたので、ちょっと拾ってきてみました。「SCATTって本当にみんなが言うほどよいものなの?」という疑問を持った方とそれに対する秀逸な回答なんかもあって有意義なトピックです。
ズールで開催されたISSFジュニアワールドカップでのSCATTトライアル
TargetTalk : SCATT Trial at ISSF Junior World Cup in Suhl
- ISSFは、ズールで開催されたジュニアワールドカップにおいて、ある「試験」を行いました。10mエアピストルのファイナルで、選手の持つピストルにワイヤレスSCATT(MX-W2)を装着し、視聴者が競技中のSCATTデータの一部を見ることができるようにしたのです。視聴者に表示されたのは、撃発直前の1秒および0.2秒を含む軌跡と、最後の0.2秒の軌跡速度です。軌跡全体が表示されることもあります。また、ホールドタイムも表示されます。これは視聴体験を向上させるためのものだとされています(笑)。APでSCATTが使用された3つのライブストリームへのリンクはこちらです。解説者によると、10m ARでもSCATTデータが表示されるとのことです(10m ARは後日実施されます)。
いくつか気づいた点があります。
1.予想されたことではあるのですが、特に序盤は時々少し不具合がありました。とはいえ混合団体決勝までにほぼ解決できたようです。
2.どうやら、電子ターゲットとSCATTが何らかの形でリンクされていたようです。(ターゲットに開く穴の位置に合わせてSCATTを定期的に調整する必要があることは承知していますが、毎回正確に合っているようでした)
3. 予選で570点以上を撃ったエリート射手(少なくとも1人のオリンピック選手を含む)のSCATTデータは、驚くほど「人間らしい」ものに見えました。最後の1秒でさえ、軌跡がバラバラになることがありました(最後の1秒で相対的な9リングを保持できなかった時もありました)。最後の0.2秒間の軌跡は、彼らのレベルの射手にとってはかなり大きく(相対的な10リングよりも大きいことがほとんど)、ずさんなトリガー操作が行われた可能性を示唆しています。最後の0.2秒間のトレース速度は、ほとんど100mm/秒を下回ることはありませんでした(ただし、0.2秒のタイトなトレースの一部は比較的高速を記録していたため、この機能に不具合があった可能性はあります(あるいは私のSCATTが壊れていた可能性もあります)。
彼らは疲れていたのかもしれませんし、決勝のプレッシャー、あるいは(取り付けたSCATTという)慣れないウエイトのせいだったのかもしれません。いずれにせよ、これは私たち凡人にとって励みと希望を与えてくれます。(10ショットフライヤー)
- 興味本位ですが、SCATTについて皆さんはどう思われますか?
ターゲットに開いた穴の位置に合わせて定期的に調整する必要があるという話は初めて聞きました。
私はピストル射撃はそこそこできる方で、上達していて国際レベルを目指しています。射撃は正確に、そして定期的に行っています。トリガーの当たり具合が悪い時やサイトアライメントが悪い時も自分で把握しています。、それだけの知識がある射手にとってのSCATTは、どのような追加メリットがあるのでしょうか?
持っている人は皆、素晴らしいと言うのですが、上記のような質問をすると、SCATTがどのように射撃に役立つのか、あるいは向上するのかを説明できないようです。
また、非常に高価なので、中古のMX-W2を売ってくれる方がいたら、ぜひ教えてください。もしそのレベルの競技会に出場するためにSCATTが必須なら、ぜひ教えてください。(ブレットP)
- SCATTは通常、射撃位置を標的上のものと正確に一致させることはできません。SCATTの真価は、電子ターゲットシステムのように射撃位置を教えてくれることではありません。SCATTの真価は、射撃位置への到達方法に関する多くの有用な情報を提供してくれることにあります。
トリガーを急激に引いたことによって7に飛ばしてしまったということは、SCATTがなくても分かります。SCATTが教えてくれることの一つは、射撃タイミングに関する詳細な情報です。SCATTのメイン画面で表示されているものは標的上での軌跡ですが、解析画面に切り替えることで表示されるタイミングトレースの方がはるかに有用だと思いますし、他にその情報を得る方法は知りません。
「ホールド」状態に入ると、通常は少し「バウンド」し、その後、最小限の揺れに落ち着きます。完全に構えた後、すぐに射撃が終わるのが理想です。複数の射撃のタイミングを検証することで、構えている時間が長すぎるのか、あるいは完全に構える前に射撃してしまうことがあるのか??が分かります。
下画像は、Noptel システム (SCATT の競合会社、現在は存在しない) から取得した良好なショットのプロットです。
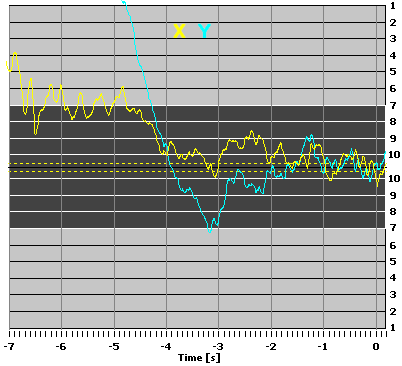
こちらは、一度上げたピストルが下がってきて、安定し、10リングでのホールド状態が安定してから約1秒後に発砲します。下手なショットの例です。
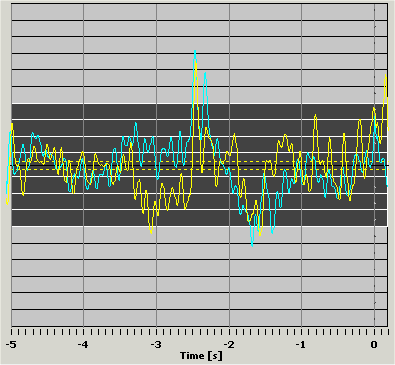
トレースが始まるまでのアプローチの長さは分かりませんが、射手は少なくとも撃発の約4秒前には9リングに落ち着いています。その後、ホールドがひどく崩れ、最終的に6点になりました。確かに、ホールドが長すぎた可能性はありますが、電子トレーナーを使えば詳細を確認できます。(Gホワイト/マサチューセッツ州)
- Gホワイトさんの意見に100%同意します。重要なのは最終結果ではありません。
私はまだ射撃経験が浅いので、私の意見は鵜呑みにしないでください。これまでのところ、このトレーニングが私に最も役立ったのは、射撃プロセス全体を通して、自分の頭の中で起こっていることとピストルで起こっていることを調整できたことです。これにより、的を絞った、意味のある調整が可能になります。例えば、以前はトリガーをしっかりと引く感覚が分かっていたと思っていましたが、SCATTデータを見て、トリガーを少し押し込んでいることが多いことに気づきました。また、最小限のブレがどれくらい続くかをよりよく理解できるようになり、その間に見て感じる動きの量に慣れ、スムーズで無意識のトリガーリリースを実行できるようになりました。他にも挙げればきりがありません。
とはいえ、採点についてですが、一度キャリブレーション(MX-W2を使用)すれば、ピストルを一定に保持し(特にトリガーリリース時の傾きが同じ)、トリガーリリース時にトレース速度が異常に高くならない限り、ほとんどの場合、穴の開きはSCATTの結果(3mm以下など)に非常に近くなります。私の推測では、SCATTがテーブルに何度も接触することで時間の経過とともに蓄積される微小な動きと、練習場所の照明条件の変化が、デバイスの調整がずれる要因になっていると思います。(10ショットフライヤー)
- ピストルに取り付けたSCATTの重さがバランスを変え、決勝に出場した選手全員の成績を悪化させたことは間違いありません。たった56グラムですから、普通は誰もそれを意識したり、練習したりしたことはないと思います。もちろん、これはピストル射撃者の場合です。
ライフル射撃者にとっては、重量増加による影響はそれほど大きくありません。(ゴーストリップ)
「普段は付けてないSCATTをいきなり強制的に銃に取り付けられたりしたら重量バランスが台無しになってしまって、そのせいで成績が落ちたんじゃないか?」というのは、実に妥当な指摘です。ピストルに取り付けるバランス調整用のウエイトって一個あたり10gとか20gで、それを銃の先っぽのほうに付けるか手前のほうに付けるかで構えたときの感覚が変わるって言われてます。そんな微妙なバランスで成り立ってるものに、56gもあるウエイトをいきなり付けられたら、いつもと全然感じが変わってしまうのは当たり前です。
※もっとも、全員が同じ条件なわけですから、フェアネスに影響があった(誰かが有利になったり不利になったりした)わけじゃないので、大会運営上で問題とされるようなことじゃないとは思います。
実際、知り合いのピストル射手の中には、普段はSCATTを取り付けて練習しているけれど試合では外さなければならない、そこで試合でも普段の練習と同じ感覚で構えられるようにダミーのSCATT(単なるオモリ)を作って試合では練習でSCATTを取り付けてるのと同じ場所にそのダミーSCATTを装着して撃つ、って人がいます。
実は私自身も同じことしてます。いつも練習してるのと同じ射場で行われた月例会で、なんか妙に銃がふわふわして安定しない、おかしーなーって思って月例会終了後にSCATT取り付けて撃ってみたら、ぜんぜん構えたときの安定感が違う!なんだこりゃ!たった40gかそこらで(有線のSCATTなので、上記のISSFジュニアワールドカップで使われたという無線のSCATTよりも軽い)こんなにも感覚って変わるもんなの?
ってことで、それ以降は試合に出るときにはSCATTとだいたい同じ位の重さになるように自作したウエイトを銃に取り付けて撃ってます。実際に効果も出て好成績を収めることができた大会もありました。
「決勝戦では出場選手全員SCATT装着を強制」ってのは、今回の中継の反応次第ではありますけれど、今後のトレンドになる可能性は十分にあります。選手としてはそうなったときでもいつも通りに撃てるような、何らかの対策が必要になってくるのかもしれません。例えば「いつでも取り外せる、SCATTと同じ重さのウエイトを装着する(普段の練習ではそのウエイトの代わりにSCATTを装着する)」みたいなやり方がスタンダードになったり、それをすることを前提としたカスタムパーツが登場したりするかもしれません。

