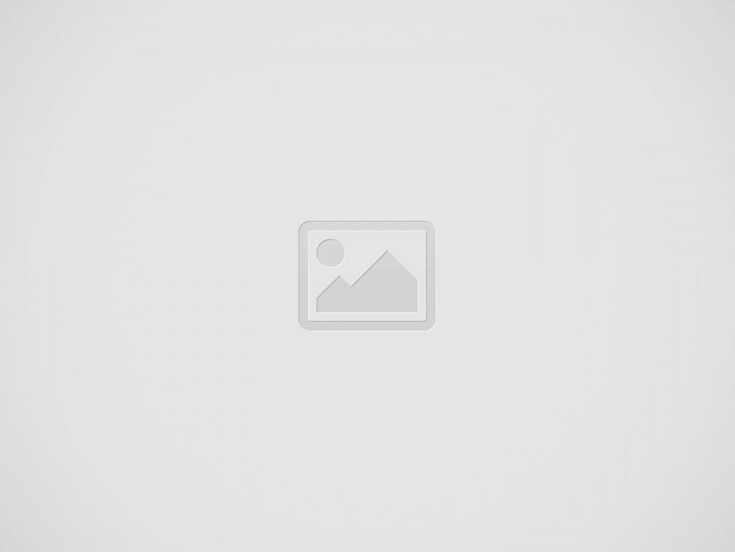

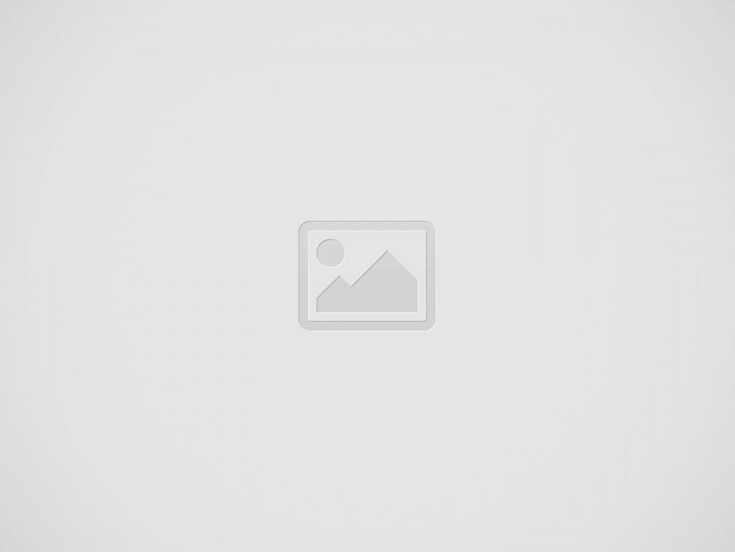

さて、今回は昨年の9月12日に参加した「ワインツーリズムを体感する旅」のリポート記事の最後になる。最後を締めくくるのは麻屋葡萄酒。創業80年の歴史あるワイナリー…というか本来の言い方をするなら「葡萄酒醸造所」だ。十数年前くらいまでなら他にいくらでもある「おみやげワイン」屋のひとつだったらしいが、跡継ぎにあたる方が「本格的なワイン」の醸造に乗り出し、国産ワインでもなかなか良いものがあるんだぞ、ということを夜に知らしめる原動力のひとつとなったワイナリーである。
醸造を担当しているのは雨宮一樹氏(プロフィールを見たところ1976年生まれとのこと、まだ三十代なんですね)。以前紹介した新宿駅地下通路に貼り出された「肉じゃがと一緒にワインどうすか」ポスターでも中心に近い位置に座っていることからも分かるとおり、勝沼の若手醸造家の中でもリーダー的な役割を果たしている方だそうだ。
この人は、基本的には口下手な方に入るのだけれど、聞いてみると話が実に面白い。さあこれから話をしてください、という状態で全員に向けて話す内容は、こういっちゃなんだけれど通り一遍の普通の内容なのだけれど、その話が終わってから個別に雑談っぽい話をするようになってからポロポロと出てくる言葉が、そのフレーズひとつだけでも記事ひとつ書けそうなほど。だから今回は麻屋葡萄酒の紹介というより、「雨宮語録」的な仕立てでお伝えしたいと思う。
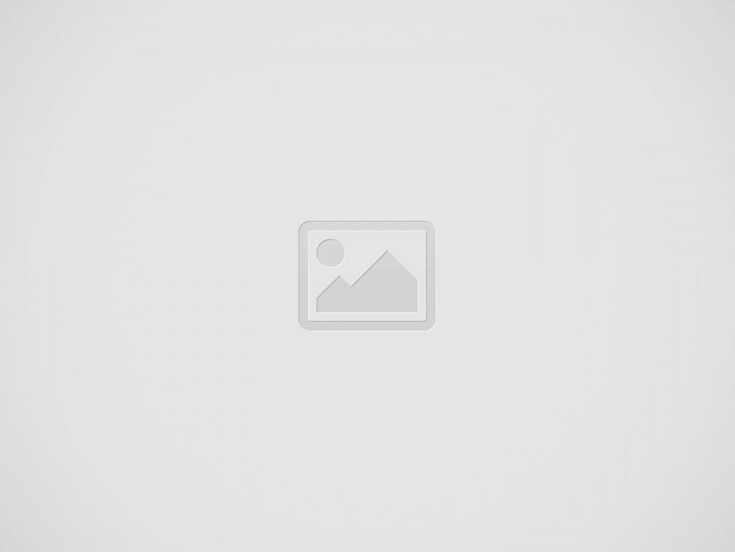

ボルドー液というのは農薬の一種で、ブドウがある程度育ったところに散布して表面に付着させることで菌類による病気を防ぐ殺菌剤だ。100年以上の歴史があり安全性は十分に確認されており、フランスなどではこのボルドー液を散布することがワイン用のブドウを栽培する上で「義務」になっているほど。
ただ、甲州種などではボルドー液の散布によって特有の香りが損なわれてしまうことが知られており、そこであえてボルドー液を使わない「ノンボルドー」という、ワイン作りとしては非常識に近い製法で作られたワインが、「香りの高い甲州ワイン」として販売されている。
こういった事情があり、「本格的にワイン作りに取り組んでいる勝沼のワイナリーなら、当然ノンボルドーにトライしているだろう」と誰もが思い質問したのだが、そういう認識を雨宮氏はいきなり真っ向から否定してしまったわけで、質問した側も半ばあっけにとられる形となった。
「日本はもともと湿気が多くカビが生えやすい。ボルドー無しでの栽培は不可能ではないがリスクが大きく現実的とは言いづらい。同じボルドー散布でも、例えば葉っぱにだけ付着させて実にはつけないとか、いろいろやり方には工夫の余地がある」
ワインの仕込みは、まず収穫したブドウを「除梗破砕機」という機械を使って、茎を取り除いて潰して絞る。その絞り汁と、茎を取り除いた実と皮を使って熟成させる。だが、麻屋葡萄酒では実と皮にさらに茎まで加えて熟成させるのだという。
その理由は、渋味を補うためだ。いわゆるワイン醸造用の品種(ヨーロッパ品種)は実が小さく皮が厚く、実と皮と絞り汁だけを使っても十分な渋味(タンニン)が抽出される。タンニンはワインの熟成によいて非常に重要な役割を果たす。渋味を嫌って軽く絞っただけの果汁を発酵させただけでは、味に深みも奥行きもない単なる「アルコール風味のブドウジュース」にしかならない。
これはひとつ上の、ワイン作りにおけるタンニンの重要度にも関連する内容だ。言葉はこう続く。「ブドウを食べたときに口に入るのは果汁だけではなく、皮や種の味や渋味もある。それらを含めて『ブドウの味』だと思う。もともと日本人はお茶の文化でわかるとおり、渋みに対する許容範囲が広い。ある程度渋みがあったほうが食卓にも馴染みやすい」
のみごろがどうだとか、コルクを抜いてからどのくらいワインが保つのかとかそういう話題の流れででた言葉だ。「果物によっては、ある程度酸化して初めて美味しくなるものだってある。例えばバナナとか、ラ・フランスなんかもそうだ。ブドウだけ、ワインだけが例外で酸化を避けなければならないという考え方自体を疑うべきだ。無添加と言うが、酵母だってSO2(二酸化硫黄)を出す」
…とまあ、こんな感じでどんどん続く。麻屋葡萄酒は、入り口にいきなり巨大なドラム缶、そして白ペンキで殴り書きされた「あさやブドー酒」の文字と、ちょっと足を踏み入れるのをためらってしまうような店構えをしているが(向かいにあるグレイスワイン=中央葡萄酒が洒落た店構えなのとは対照的)、中に入れば洒落た試飲室もあり、運がよければ上記のような雨宮氏の炸裂トークを聞くこともできる、一見の価値ありなワイナリーである。